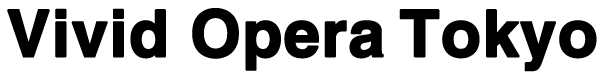さて、今回は語学というよりはディクションの話です。
私はディクションというものが大好きです。小さい頃にアメリカに住んで米語に触れた経験からでしょうか、それぞれの言語が持つ独自の響き、その音声の違いが面白くてたまりません。調音音声学も、IPA(国際発音記号)も大好きです。
でもディクションって、一つ一つの音節が「正確に」発されていれば良い、というものでしょうか?日本語を母語とする人の音声を採取して分解し、コンピュータで繋ぎ合わせたら、それは「良いディクション」なのでしょうか?
違いますよね。
こんなことを考えている傍で、レイナルド・アーンの"On Singers and Singing"(仏語原題:"Du chant")という講義集を読んでいたところ、ディクションに関して眼からウロコな文章を発見したので、ちょっと和訳してみました。
★ アーン先生のパワーワード:「歌は小川」
★ アーン先生のキメ台詞:「真に説得力のあるディクションは、歌手の魂と精神から生まれる」
◆
[単なる明確な発音に対し] ディクションとは、発音の美学です。それは、「語り口」における複数のメカニズムを司り、バランスを取り、飾り立てる、最も重要な支配的存在です。我々が物事を語る時、ディクションはそこに多様性と表現をもたらすのです。
ディクションにはたくさんの要素がありますが、ここでは最も重要なものだけを挙げてみましょう。それは、素速さの度合いや、単語やフレーズの一部、またはフレーズ全体における間の取り方。更に、ディクションは声に脈絡を与え、力強い/優しいニュアンスを授けます。また声の響き方と動き方に、微かだったり強力だったりする、グラデーションを与えます。
「ディクション⇔言葉」の関係は、「眼差し/表情⇔目そのもの」と同じです。ディクションは言葉に生命を与え、構文に思考と感情を注入します。
そこで、大変多くの「良く歌える(少なくとも、悪くなく歌える)歌手」に欠けるものが浮かび上がりますね—彼らの発声は真っ当で、発音も正確で明確だが、しかし何も語らない。
いや、「良く歌える」と言ったのが間違いでした。彼らは歌えます…厳密に言うと、発声は正しいのです。しかし彼らは、「声が芸術的な機能を全うする」という側面において、「良く」は歌えていないのです。そのような歌唱において、声は言葉から分離し、両者は一体にならず、平行線を辿ります。声は言葉によって満たされるということもなく、声は言葉と協働しません。
ちょっと付け加えさせてください:実に面白く不思議なことに、このような歌唱には、声の究極の美しさが欠けているのです。なぜなら、そのような美しさは実に、ニュアンスと多様性によって成立するからです。言葉によって命を吹き込まれていない、言葉によって導かれ統制されていない、言葉に従属していない—そのような歌唱は、単調なものです。それは明るかろうが暗かろうが、眩しかろうがどんよりしていようが、モノクロの世界に過ぎません。それは違う色相になれず、色彩や陰影が変化することもないのです。この変化のない歌唱など、死んでいるも同然です。
一方で、これらの色彩が声に現れる時、その歌唱はまるで、通り過ぎる空の微妙な色彩を映し出す小川のようです。[…]このように、歌唱はその針路と動きにおいて、私たちの魂の全ての色を反映させなければいけません。
私たちが、フレーズもしくはフレーズの連なりを発音するとき、精神状態が激しく変わることはないでしょう。私たちの気分はそんなに素早く変化しません。しかし同じ精神状態の中においての、波動や振動は無限です。下手な俳優は一語ごとに顔の表情を変えますが、長いセリフを全て単調に語るのはもっと酷いです。言葉に何の抑揚も与えず、ほんの僅かながらも何より重要なニュアンスも与えない…抑揚とニュアンスは、思考と感情の変動によって、当然存在するべきなのです。
なので、真に説得力のあるディクションは、歌手の魂と精神から生まれると言えるでしょう。
Reynaldo Hahn: On Singers and Singing (Amadeus Press, 1957=1990) III. How to Enunciate in Singing
◆
これを読んだ時、「ほんとうに、だから語学をやらなければいけないのだ」と強く思いました。歌詞で扱う言葉に、リアルタイムで「魂の色を反映させられる」というのは、言語自体の理解なしには起こり得ません。逆に言えば、言語のしっかりした理解があれば、あれこれ味付けを加えるよりも余程効果的で自然な「多様性と表現」が得られるということですね。
あ〜、もっと言語できるようになりたい。😩